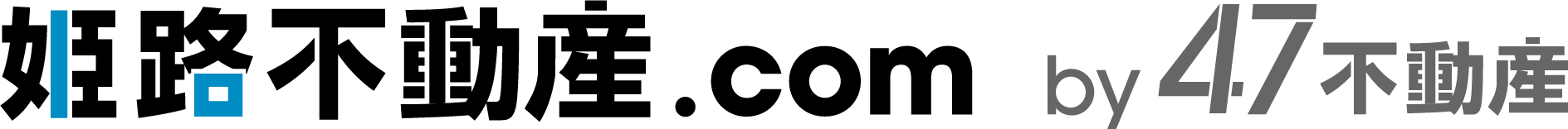近年は共働き夫婦が増えたこともあり、夫婦2人で住宅ローンを組むケースが多くなっています。
内閣府の「男女共同参画白書 令和4年版」(2022年)によると、働く夫と専業主婦の世帯は減少し続けていますが、共働き世帯は増加中です。
2001年から2021年までで約1.5倍も増加しており、夫婦のいる世帯全体の約7割にまで達しています。
そこで今回は近年増えているペアローンの、メリットとデメリットをご紹介させていただきます。

1,夫婦2人で住宅ローンを組む方法は大きく2つ
・ペアローン型
・収入合算型(連帯債務・連帯保証)
上記の住宅ローンはどちらも、夫婦互いが連帯責任を負うことになります。
収入合算型には連帯債務、連帯保証の2パターンあります。
そこで、まず理解しておいてほしいのが「連帯債務」と「連帯保証」の違いです。
連帯債務と連帯保証は、同じ連帯責任を負うにしても、下記のように責任度が大きく異なります。
【連帯債務】
夫婦どちらかが主債務者となり、残りの一報が連帯債務者となること。
主債務者の返済能力にかかわらず、常に主債務者と同じ返済義務を負います。
【連帯保証】
夫婦どちらかが契約した住宅ローンを、残り一方が保証すること。
主債務者が返済不能となったときに、返済責任が生じます。
どちらのタイプを選ぶかによって、負わされる責任度は大きく違います。
連帯債務の場合は債務者と同じ返済義務を負う一方、連帯保証の場合は債務者が返済不能になったときに返済義務を負います。
2,ペアローンを組むメリットは
ペアローンを組むメリットは、借入金額を増やせるほか、住宅ローン控除や団体信用生命保険に夫婦それぞれで加入できるというメリットがあります。
①借入金額を増やせる
一般的に収入合算型の場合、夫婦の合計の年収で借入額の審査を行っていきます。
おおざっぱには年収の7倍まで借入ができます。
例えば、それぞれ年収が400万円と仮定すると
1人で借入れをする場合は2800万円まで、
2人で合算して借入をする場合は5600万円まで借入が可能となります。
1人より2人の場合の方が借入額が増えます。
②住宅ローン控除をそれぞれ受けれる
共働き世帯の場合、それぞれで国税(所得税)と地方税(住民税)を支払っています。
税負担は家計にも大きいです。
1人で住宅ローンを借りた場合は、借りた人の税金から控除されます。
借入額がおおく控除対象の限度額を超える場合はそれぞれから控除する方がお得になるケースが多いです。
つまり夫婦間の状況や借入額によってローン控除のメリットを大きくする効果があります。
3,住宅ローンの連帯責任で夫婦に起こりうる問題
ペアローンを使う場合、大きく下記の3つの事項で問題が生じるケースがあります。
これらが、ペアローンのデメリットともいえます。
ただし、しっかりと理解して
①どちらかに万が一のことがあった場合の団体信用生命保険
大抵の住宅ローンでは、団体信用生命保険(以下、団信)の加入が求められます。そのため、債務者死亡時にはローン返済が免除されるのが一般的です。
しかし、夫・妻ともに債務者であるペアローンの場合、免除されるのは死亡した債務者分だけになり、残された一方の返済は免除されません。
こちらは、金融機関によって、どちらかが一方死亡した場合全額免除される団信もございます。
金融機関の商品をよく見て、決めれば万が一の時の問題も防げます。
②離婚時
離婚したから連帯債務や連帯保証から外れたいと考える人が多いです。
しかし、これら連帯責任から外れるのは容易ではありません。
連帯責任から外れるには
・住宅ローンを完済する
・自身に代わる連帯債務者・連帯保証人を探す
ですが、他の保証人を探すのは難しいケースが多いです。もし該当者がいたとしても、ローン会社の審査を通過する必要があります。
一番多いのはローン完済する方法です。住宅は資産なので、売ることが可能です。
ローン残債が売却額より小さければ、売却して完済することが可能です。
③税金の問題
一番問題になるのが「贈与税」です。
以下の場合は、贈与税の対象となり課税されるケースもあります。
・債務者・主債務者の返済分を、一方の資金で繰り上げ返済した場合
・ペアローンの繰り上げ返済で、一方がそれぞれの持分割合を超えた返済をした場合
日常生活で通常必要になるお金の授受には、贈与税は課税されません。しかし、住宅ローンは「日常生活で通常必要になる資金」とはみなされないので年間110万円を超える場合、課税されることになります。
しかし、婚姻期間が20年を超えていれば税額控除が受けられます。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」により、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までの税金控除が受けられます。
(参照:国税庁HP)
4,まとめ
これまで、夫婦ペアでローンを借りる場合のメリットとデメリットをご紹介してきました。
夫婦のご状況等により、メリットが多い場合、それほどメリットが無い場合があります。
メリットとデメリットをよく理解した上で、検討されることをおすすめいたします。
より詳細なことは、弊社スタッフまでご相談ください。
姫路不動産.com 47不動産